コンピューター
ナビゲーションに移動
検索に移動
コンピューター(英:Computer )とは、人間に代わって、自動的に複雑な計算を行う計算機。人間には簡単にはできないことや、面倒なことを、早く正確に行うことができる。コンピュータと伸ばさない表記が後から主流になった[1]。現代社会の私達には欠かせない機械である。
概要[編集]
初期のコンピューターは歯車式で、機械的に計算を行なっていた[2]。その後真空管や半導体など電子的な仕組みを用いるようになった。弾道計算やマンハッタン計画で用いられていたという話は有名である[3]。
現代のコンピューターの電源を入れると、まずBIOSが起動し、更にBIOSによってOSがローカルディスクやローカルネットワークから読み込まれることによって初めて、私たちの知る『コンピューター』として使うことができるようになる。
コンピューターの構成要素としては、物理的な実体を持つ「ハードウェア」と、物理的な実体を持たない「ソフトウェア」に分けられる。ハードウェアは機械の部分で、ソフトウェアはプログラムの部分である。
代表的なハードウェア[編集]
コンピューターの本体は、基本的に、CPUと各部品(外付け部品の場合は差し込み口)を信号線でつないだものである。
なお、制御、演算、記憶、入力、出力の各装置を合わせて「五大装置」と呼ぶ。
電気回路[編集]
- ACアダプタ (ラップトップ)
- コンセントから引いてきた強い交流電流を、精密電子部品に適した弱い直流電流に変換するもの。ラップトップに必要な電力は、ACアダプタを通して供給される。なおデスクトップの場合は電源ユニットと電源コードがこの役目を担う。
- 電源ユニット(デスクトップ)
- コンセントから引いてきた強い交流電流を、精密電子部品に適した弱い直流電流に変換するもの。コンピューター本体に内蔵されることが多く、サイズが大きく重いため下の方に配置されている。
- マザーボード

- 各種ハードを繋げる役割を持っている。通常、CPU、メモリ、グラフィックボード、LANボードの差し込みの多くはマザーボードに設けられている。
- コンピューターの電源投入時にはまずマザーボードが起動し、BIOSと呼ばれる制御プログラムが起動し、各種ハードのチェックが走る。異常があるとビープ音が鳴ったりしてユーザーに通知する。
- 機能拡張用のスロット等を多数備えており、各種機能を拡張できる場合が多い。
制御装置、演算装置[編集]
- CPU(中央演算処理装置)
詳細は「CPU」を参照
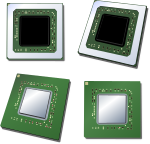
- シリコンで出来た電子回路により、命令やデータを取り出し、各種計算を行う。
- 基本的にメインメモリ上のデータにアクセスするが、L1キャッシュ、L2キャッシュといったキャッシュも備えている。
- 8ビットCPUや16ビットCPU、32ビットCPUや64ビットCPUという呼ばれ方は、そのCPUが一度に扱えるデータ量と関連している。
- 例1) 8ビットCPU:Zilog Z80、Intel 8008など。
- 例2)64ビットCPU:Intel Core iシリーズ、Xeonなど。
記憶装置[編集]
- メインメモリ、物理メモリ(主記憶装置)
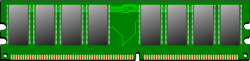
- シリコンで出来た電子回路によりデータを記憶する。CPUが直接情報を読む事が出来る。
- 補助記憶装置に比べると高速で読み書きが出来るが、電源が断たれるとデータが消えるという特徴がある。
- 記憶装置全体を机に例えると、主記憶装置が机の上、補助記憶装置が引き出しに相当する。
- ストレージクラスメモリ
- 主記憶装置と補助記憶装置の速度差を補うべく、注目されるようになった不揮発性メモリ。
- こちらもキャッシュのようで、SSDよりも速度が早い模様。
- ストレージ(補助記憶装置)


- HDDやSSD、USBメモリなど。主記憶装置に比べると、データの読み書き速度は劣る。
- コンピューターに電源が投入された際にはBIOSによって補助記憶装置から主記憶装置にOS本体が読み込まれる。その後、OSによってOSの動作に必要なプログラム等のデータがロードされる。
- コンピューターの電源OFF時にもデータは消失しない。
- 多くのOSには、主記憶装置の容量が不足している際に、「仮想メモリ」(スワップ)というデータを補助記録装置に書き込み、主記憶装置に代わって記憶する機能がある。これが頻繁に発生するような構成だと、補助記憶装置と主記憶装置の間でのデータのやり取りが頻繁に発生し、動作速度が落ちる。
- 特にアクセスの多い業務用コンピューターではHDDではI/Oがボトルネックになる事が早期に判明し、SSDへの切り替えが進んだ。個人用のパソコンでもHDDではなくSSDにOSを入れると起動速度が改善される事例が多い。
- 記憶装置全体を机に例えると、補助記憶装置が引き出し、主記憶装置が机の上に相当する。
入出力装置[編集]
- グラフィックボード (GPU)
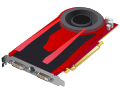
- マザーボードと外部モニターの間に介在する、映像出力用の基板。各種演算が行える場合もある。
- マザーボードにオンボードで実装されていたり、CPUに内蔵されていたりする場合もある。
- 内蔵されていないグラフィックボードは、ビデオカードとも呼ばれる。
- LANボード

- マザーボードとネットワークケーブルの間に介在する、ネットワーク接続用の基板。マザーボードにオンボードで実装されていたりする。Network Interface Card、NIC、ニックと呼ばれる事もある。
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Z
X
C
V
B
N
M
一般的なソフトウェア[編集]
- 一口にソフトウェアと言うと、プログラミングされたプログラムを指す。
- アプリケーション・ソフトウェアとミドルウェア、オペレーティングシステムに分類されることとアプリケーション・ソフトウェアとシステムソフトウェアに分類されることがある。
- 用途別に分類でき、オペレーティングシステムやアプリケーション、表計算ソフト、文章作成ソフト、テキストエディタ、各種ゲーム等が挙げられる。
- 何か新しいハードウェアを使用する際にインストールするドライバやファームウェアもソフトウェアに分類できる。
その他[編集]
CPUクーラー等、コンピューターのシステム的には必須なパーツでも、情報処理や計算には直接関係無いパーツはハードウェアには分類されない事もある。






